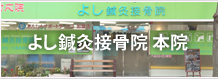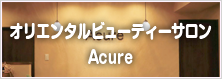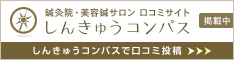お知らせ
グロインペイン症候群を徹底解説
2025-10-17

こんにちは。
大阪府東大阪市吉田6丁目
東花園駅前 ロータリー沿いのマンション1階にあります
よし鍼灸接骨院 東花園院です。
長年多くの選手のサポートをしてきましたが、特にサッカーなど、激しい動きを繰り返すスポーツに打ち込む選手が悩まされがちなのが、股関節周りの痛み「グロインペイン症候群」です。
「足の付け根が痛いけど、ただの筋肉痛かな?」「練習を休むべきか迷う…」そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
この痛みは単なる筋肉の張りではなく、身体全体の使い方のアンバランスさを示す重要なサインであることがほとんどです。
今回は、グロインペイン症候群について初めて知る方でも安心して読み進められるよう、その正体から原因、そして今日から自分でできるケア、さらには再発させないための身体づくりまで、分かりやすく丁寧に解説していきます。
一緒に正しい知識を身につけ、ケガを乗り越えていきましょう!
2014年に「ドーハ分類」という国際的な合意がなされ、現在は主に以下の5つのカテゴリーに分けて考えられています。
・ 内転筋関連: 太ももの内側の筋肉が原因の痛み
・ 腸腰筋関連: 股関節の付け根の奥にある筋肉が原因の痛み
・ 鼠径部関連: 鼠径部のトンネル状の構造(鼠径管)周辺が原因の痛み
・ 恥骨関連: 骨盤の前中心にある恥骨が原因の痛み
・ 股関節関連: 股関節そのもの(関節唇損傷など)が原因の痛み
このように、痛みの原因は多岐にわたり、複数の要因が複合していることも少なくありません。
だからこそ、自分の症状を正しく理解することが、回復への第一歩となります。
まずは、ご自身の状態と照らし合わせてみてください。
1ヶ所だけでなく、広い範囲にわたって痛みが出ることが特徴です。
・ 鼠径部(そけいぶ):足の付け根のV字ラインの部分
・ 太ももの付け根(内側):内ももの一番上のあたり
・ 下腹部
・ 恥骨(ちこつ)周辺
・ 初期段階(軽度)
・ダッシュやキックなど、激しい運動中にだけ痛みを感じる。
・運動を終えると痛みは自然に治まる。
・ 中期段階(中等度)
・ウォーミングアップや軽いジョギングなど、これまで問題なかった動きでも痛みを感じ、運動後も痛みが残るようになる。
・朝起きたときに股関節周りに違和感を覚えることがある。
・ 重度段階
・安静にしていてもズキズキと痛む。
・歩行や立ち上がりなど、日常生活の何気ない動作でも痛みを感じる。
・夜間の痛みで眠れなくなることもある。
これらの症状に心当たりがある場合、放置は禁物です。
2. なぜ起こるの?グロインペイン症候群の主な原因
グロインペイン症候群は、単一の原因ではなく、いくつかの要因が複雑に絡み合って発症します。
大阪府東大阪市吉田6丁目
東花園駅前 ロータリー沿いのマンション1階にあります
よし鍼灸接骨院 東花園院です。
長年多くの選手のサポートをしてきましたが、特にサッカーなど、激しい動きを繰り返すスポーツに打ち込む選手が悩まされがちなのが、股関節周りの痛み「グロインペイン症候群」です。
「足の付け根が痛いけど、ただの筋肉痛かな?」「練習を休むべきか迷う…」そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
この痛みは単なる筋肉の張りではなく、身体全体の使い方のアンバランスさを示す重要なサインであることがほとんどです。
今回は、グロインペイン症候群について初めて知る方でも安心して読み進められるよう、その正体から原因、そして今日から自分でできるケア、さらには再発させないための身体づくりまで、分かりやすく丁寧に解説していきます。
一緒に正しい知識を身につけ、ケガを乗り越えていきましょう!
そもそもグロインペイン症候群とは?
まず理解しておきたいのは、「グロインペイン症候群」は特定の病名ではなく、股関節周辺に起こる痛みの「総称」だということです。2014年に「ドーハ分類」という国際的な合意がなされ、現在は主に以下の5つのカテゴリーに分けて考えられています。
・ 内転筋関連: 太ももの内側の筋肉が原因の痛み
・ 腸腰筋関連: 股関節の付け根の奥にある筋肉が原因の痛み
・ 鼠径部関連: 鼠径部のトンネル状の構造(鼠径管)周辺が原因の痛み
・ 恥骨関連: 骨盤の前中心にある恥骨が原因の痛み
・ 股関節関連: 股関節そのもの(関節唇損傷など)が原因の痛み
このように、痛みの原因は多岐にわたり、複数の要因が複合していることも少なくありません。
だからこそ、自分の症状を正しく理解することが、回復への第一歩となります。
1. もしかして?グロインペイン症候群の主な症状
痛みの場所を一言で「足の付け根」と言っても、人によって場所や痛みの強さが異なります。まずは、ご自身の状態と照らし合わせてみてください。
痛みの場所
痛みや不快感は、主に以下の範囲で感じられます。1ヶ所だけでなく、広い範囲にわたって痛みが出ることが特徴です。
・ 鼠径部(そけいぶ):足の付け根のV字ラインの部分
・ 太ももの付け根(内側):内ももの一番上のあたり
・ 下腹部
・ 恥骨(ちこつ)周辺
症状の進行度
この疾患は放っておくと症状が段階的に悪化していく傾向があります。・ 初期段階(軽度)
・ダッシュやキックなど、激しい運動中にだけ痛みを感じる。
・運動を終えると痛みは自然に治まる。
・ 中期段階(中等度)
・ウォーミングアップや軽いジョギングなど、これまで問題なかった動きでも痛みを感じ、運動後も痛みが残るようになる。
・朝起きたときに股関節周りに違和感を覚えることがある。
・ 重度段階
・安静にしていてもズキズキと痛む。
・歩行や立ち上がりなど、日常生活の何気ない動作でも痛みを感じる。
・夜間の痛みで眠れなくなることもある。
これらの症状に心当たりがある場合、放置は禁物です。